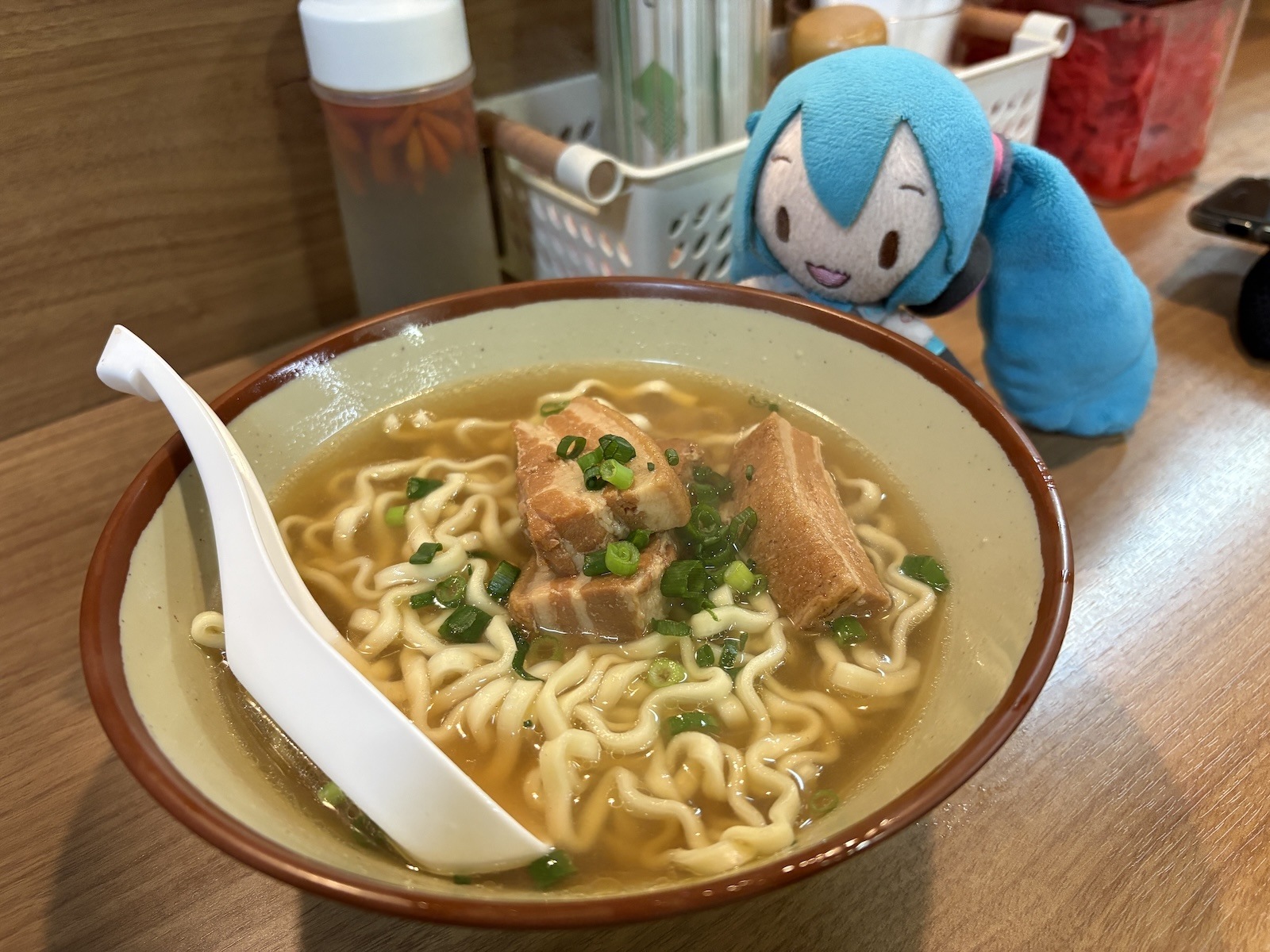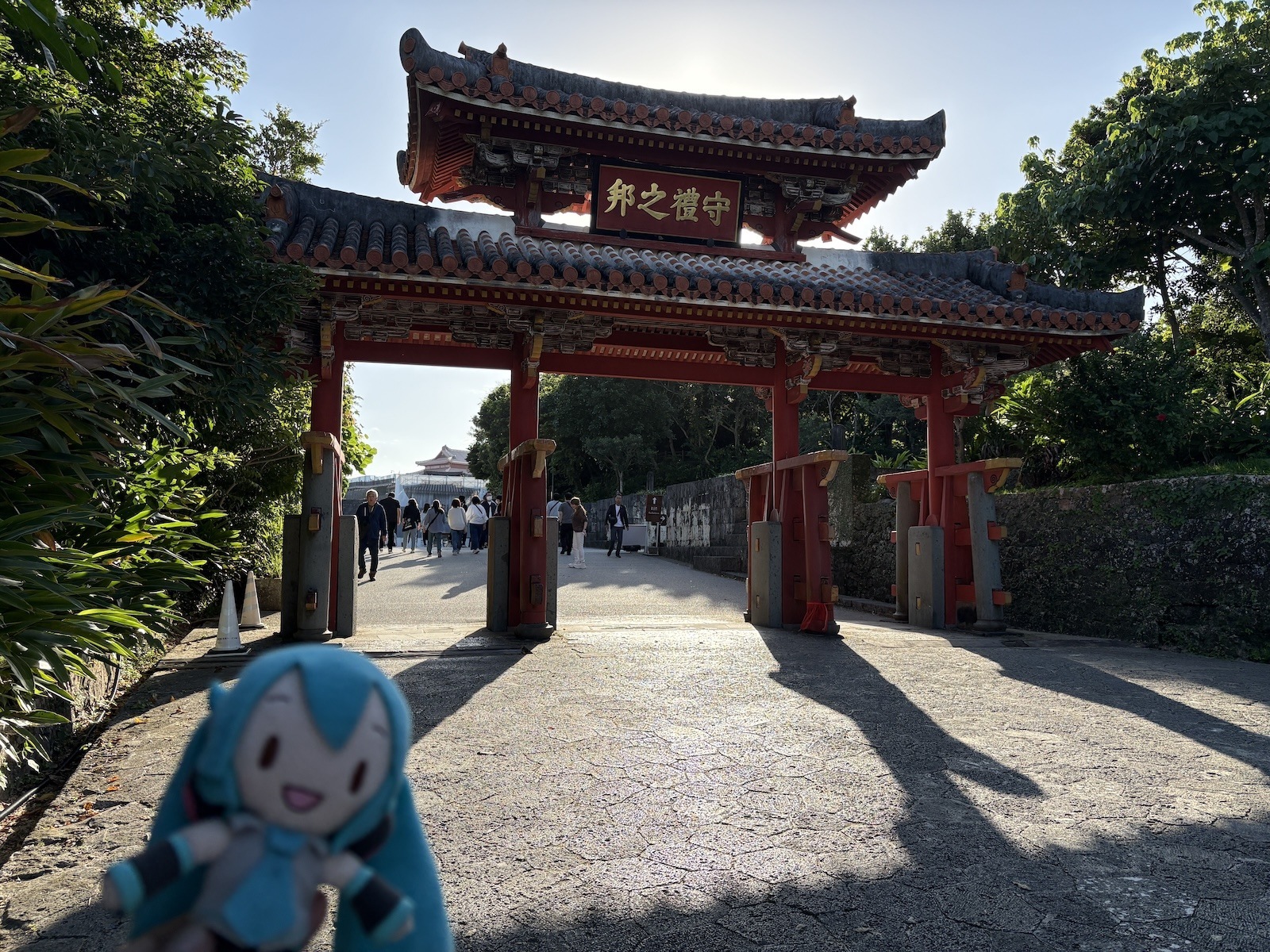べつに今年は完走を目指してはいないのですが、Raspberry Pi Advent Calendar 2025の5日目です。
Raspberry Pi Advent Calendar 2025 - Adventar
Raspberry Pi OSの2025/12/4版がリリースされていたので拾い読みしつつ、それだけだと何なので、今年のPi 4とPi 5のEEPROM更新について振り返ってみようと思います。
Raspberry Pi OS 2025/12/4版
各種不具合修正と改善といえばそれまでですが、いろいろ修正したようです。ファームウェアとLinuxカーネルも前回から変更はありません。
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_armhf/release_notes.txt
2025-12-04: * Added ability to safely eject HDD and NVMe drives connected via USB * Added Alt-F2 shortcut to open run dialog in labwc desktop * Screens control panel no longer creates a default kanshi config file when started * Bug fix - crash when using mounted drives or wastebasket in Places view * Bug fix - crash when unloading system monitor plugin * Bug fix - crash when power-cycling audio devices * Bug fix - Bluetooth plugin icon not being hidden correctly on devices with no Bluetooth hardware * Bug fix - crash in file manager which switching to a TTY * Raspberry Pi firmware 676efed1194de38975889a34276091da1f5aadd3 * Linux kernel 6.12.47 - 359f37f0faefb712add32a39f98751aea67d5c1f
今年のEEPROMアップデートふりかえり
Pi 4/Pi 5のEEPROMイメージの更新は、コミットが出るたびにMastodonの方で雑にコメントをしています。
EEPROM の検索結果 - @akkiesoft@social.mikutter.hachune.netの投稿 - notestock
2025-01-06版(2712)では、Pi 5起動時のファン回転時間が減る変更が来ていました。あれそんな最近でしたかね(ジジイ)。翌日にはすぐに修正が入っていたようですが。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/113784209535533585
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/113789798960845146
2025-01-13版(2712)は、Pi 5 16GB向けのメモリの調整。出荷時から更新すると、メモリ性能が改善される系のやつでした。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/113821833100906321
2025-01-14版(2712)は、ワンタイムブートっぽいやつの実装。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/113827570571093294
2025-02-11版は2711と2712両方。共通する機能は両方更新されることがあります。そして、CM5向けの、Wi-Fiがないモデルの電力出力の改善。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/114013990283592506
めた先輩が、rpi-eepromをAlmaLinuxに含めるにあたり、ライセンス情報がPi4の頃から更新されていなかったので、問い合わせて更新してもらったという内容ですね。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/114025557691012912
2025-05-08版(2712)と2025-02-24版(2711)は、インターネットブート機能のTCPの性能改善。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/114475276402421554
2025-06-20版(2712)は、ウォッチドッグ、OSでしかやってしなかったファン制御用の温度監視をファームウェアでもやる改善、SDカードが刺さってないときにブート順からSDカードをスキップする改善。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/114718693076879104
2025-09-22版は2712と2711両方のリリース。ブートローダーの解凍にLZ4のサポートが追加されました。圧縮率がLZ4のほうが良いのでということで追加された模様。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115248990892704926
2025-09-25版(2712)はUARTのボーレート変更に対応。いじりたい人いるんかなって言ったら、いじりたいっしょって言われたようなうろ覚え。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115267762777902626
2025-10-08版(2712と2711)。Pi 5はNVMe ドライブの4Kネイティブセクタの暫定サポートが入りました。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115341400162936642
2025-10-17版(2712)は、D0ステッピングでのパフォーマンス改善、GPTパーティションのネイティブ4Kサポートが入りました。rpibootの検出方法の変更はこの数日前に2711向けにもリリースされています。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115391975246404823
2025-11-05版は2711と2712両方で、Fake NUMAの問題によって、一部ベンチマークでパフォーマンスが悪かった問題が修正されています。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115500578837689258
2025-11-27版も2711と2712両方で、複数USB MSDを接続した場合のブート失敗?に関する不具合が修正されているようです。
https://social.mikutter.hachune.net/@akkiesoft/115624680777369926
さて、長くなりましたが、こうしてみると、今年もちまちまと修正とか改善が盛り込まれていることがわかります。実際にはこれらで全部ではなく、産業向けを意識したような、一般ユーザー?からしたらよくわからんような変更もいろいろ入っています。そして、Pi 4向けの改善もまだ積極的に行われていることがわかりますね。
お手持ちのPi 4、Pi 5も、気が向いたら更新してあげてみてください。